松本さんのはなし
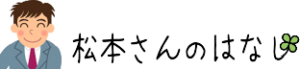
~松本さんのはなし(26)~
2025年も後残りわずかとなりました。クリスマスや冬休みを前にしたこの時期、各地区で子ども会の行事が盛んに行われる時期でもあります。
少し前にはなりますが、市子連行事も振り返ってみることにします。9月28日(日)第54回高松市子ども会フットベースボール大会を(昨年は途中大雨が降って中断、そして、中止となってしまいました)今回は爽やかな晴天のもと、また、気温の方もあまり高くなく熱中症を心配することもない状況で、無事に行うことができました。フットベースボール大会は年々出場チームが減少傾向にあります。私が子どもの頃(何十年も昔)はフットベースボールを学校の体育の授業でもしていた記憶がありますが、近年は殆ど学校ではしなくなってしまいました。時代に即して子ども会のスポーツ大会も学校でもやっていて、子どもたちも取り組みやすい内容に柔軟に替えていかねばと思っています。現在、皆さんの意見も取り入れて、2年後は替える方向で準備を進めています。(来年は節目の55回となりますので、最後のフットベースボール大会をする予定です。)
11月 8日(土)には、香南アグリームにて子ども会リーダー研修会を開催しました。今回の内容は収穫体験と餅つきです。収穫体験では、サツマイモ堀りと柿の収穫をしました。今年は夏が暑かったこともあり、サツマイモの出来具合が悪いと施設の人から聞かされていましたが、それでも子どもたちは、宝探しでもするかのように土を丹念に掘って立派なサツマイモを掘り出して歓声をあげていました。
一方柿の方は豊作で、枝が垂れ下がるほどたわわに実をつけていました。「形が良くて、あまり赤くなり過ぎてない柿を採りましょう。」という施設の方のご指導で、子どもたちは迷ってしまうほどたくさんある柿の中から、よく見て自分で選んで採っていました。
その後は餅つきです。餅は施設の方がつけばいい状態にまで準備してくれていました。(ここまでするのが大変なのですが)子どもたちの中には経験の無い子どもも半数以上いましたが、大人たちの助言やかけ声のもと、慣れない手つきで、ついて、丸めてと頑張っていました。以前はお正月が近くなると、家々で餅つきをしていましたが、そうした伝統行事的なものも少なくなっています。
今回のリーダー研修会も子どもたちにとって良い経験になったことだと思います。
子どもの時に体験したことは一生忘れないといわれています。市子連ではこうしたリーダー研修会等を通し、実体験にもとづく体験活動をこれからも多く実施していこうと思っています。
今現在は、来年2月1日(日)に開催される「新春子どもフェスティバル2026」に向けて、おまつり部が中心となって準備を進めています。今回は中央公園が改修工事になっているため、場所や内容が例年と変わっています。実施要項をよく確認してください。(実施要項は市子連ホームページにも掲載されています)
「さむさに まけるな かぜのこ よいこ」のテーマのもと子どもたちも大人の方も楽しんでもらえる一日にしていこうと思っています。
本年も子ども会活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。
よいお年をお迎えください。
~松本さんのはなし(25)~
9月に入り、小学校では2学期が始まっています。まだまだ暑さが続く中、子どもたちの中には日傘を差して登下校する姿をよく見かけるようになりました。ランドセルに水筒、手提げの荷物とプラス日傘、大変な格好です。(私の小学校時代には無かったような光景です)今年の夏は気象だけでは無く、子どもたちの格好にも異常さを感じてしまいました。
市子連行事に各校区の子ども会リーダーを対象としての子ども会リーダー研修会があります。例年夏休み前と秋または冬の年二回開催しています。今年度の、夏休み前のリーダー研修は、7月 5日(土)、高知の夜須でYASU海の駅クラブさんのご協力のもとシーカヤックやサップなどの海の活動をしました。その後、少しは涼しいのではと、日本三大鍾乳洞の1つ龍河洞の見学をしました。
真夏の太陽の日差しが強い時期ではありましたが、高知は海風があるせいか意外と高松よりも気温も低く感じられました。海の活動では、インストラクターの皆さんのご指導でライフジャケットを正確にしっかりと装着し、シーカヤックやサップに挑戦、最初は慣れないようでしたが、さすがに子どもたちは飲み込みが早く楽しく操作をすることができていました。こうした海の活動に付随する形ではありますが、海や川で遊ぶときには必ずライフジャケットを着けなくてはと、感じてもらえたかなと思っております。夏休みに海や川での事故を毎年聞きます。ライフジャケットは欠かせないものだと、大人の私も着けていてそう思いました。
龍河洞では中に入ると涼しく見学することができました。鍾乳石は100年で約1センチしか成長しなく、目の前にある光景は約1億7500万年の歳月がかかっているとの説明を聞きました。まだ生まれて十数年の子どもたちの心に何かが残ってくれればいいのにと思いながら、回りました。
9月 28日(日)には市子連行事のひとつである子ども会フットベースボール大会を開催する予定です。その頃にはもう少し暑さも和らいでいることと思っていますが、気象予報では10月頃まで暑さが続くとのこと。熱中症に気を付けて、暑さ対策を万全に、楽しいフットベースボール大会にしようと、今、体育部が中心となって準備をしています。スポーツは子どもたちにとって心や体を成長させる力があります。勝敗にこだわること無く子ども会らしく、また、他校区の子どもたちとも友好が深まる大会にしていきたいと思います。
近年フットベースボールは学校の体育の授業でもすることがなくなってしまいましたが、ソフトボール、野球、サッカー、ドッチボールが組み合わさったような特徴ある独特な球技です。試合にはエントリーされていない校区の方も高松市西部運動センターで9時30分開始ですので、ぜひ、子どもたちの真剣に取り組む姿を見に来てください。
~松本さんのはなし(24)~
新年度になって2か月、季節は梅雨に入って、ジメジメとした天候が続いています。この4月に入学したばかりの1年生も運動会で一生懸命に練習した演技を元気よく披露していました。
そうした中、市子連では5月10日(土)に、大西市長様、小柳教育長様をはじめとしたご来賓の皆様のご臨席のもと、令和7年度の総会を行いました。はじめに、長年、校区の会長や市子連理事として、ご貢献された方々に、育成功労者感謝状の贈呈を行いました。多方面において市子連の活動を支えてくださり、本当にありがとうございました。今後も地域や子どもたちのため、また、後継される方に培われた経験を活かして、お力添えをいただけたらと思います。また、議事につきましても、皆様のご協力により、無事承認をえることができました。ありがとうございました。
そして、6月 7日(土)には、主に新たに子ども会の役員になられた方を対象としての新役員講習会を、しおのえセカンドステージにて行いました。この講習会は例年夏休みを前にして、子ども会活動が盛んになるこの時期に行っています。今回は、役員を引き受けたものの何をしたらいいのか、また、市子連のことがよく解らないなど、不安に感じている方も多くいるのでは……と言うことで、市子連行事の紹介と説明をしました。また、市子連のホームページをスマホから開いてもらって、その紹介と活用についても話をさせてもらいました。
その後、「新春子どもフェスティバル」のかるた大会で行われているかるたを実際に体験していただきました。読みに関しても人が読むのとアプリを使っての読み(日本語バージョン)、そして英語版があるのでその体験も少し紹介とともにしました。このかるたは「高松わくわくかるた」と言います。コロナ禍で行事ができなかった時、市内の子どもたちに募集をして作りました。高松の名所や名物、お祭りや方言など高松の魅力がいっぱい詰まったかるたとなっています。子どもたちが将来、高松から遠くへ巣立っていくことがあっても、ふるさと高松を思い起こせるかるたです。
それから、後半には、現在何かと物議を醸し出している「米」、その米の袋を使ってのバッグを作りました。どのようなバッグができるのか少し心配でしたが、結構丈夫で個性的なバッグを、コミノ米袋ワークショップさんの指導のもと、皆さん作業時間1時間程度で完成させていました。このバッグを見る度に米の値段が高騰して、備蓄米が……と言うことを思い出すことだと思います。
7月5日(土)には子ども会リーダー研修会を行う予定です。高知のYASU海の駅クラブでシーカヤックなどの体験や龍河洞に行きます。ぜひご参加ください。(詳しくは、このホームぺージにある要項をご覧ください)お待ちしております。
子どもの時に経験し、体験したことは一生忘れないと言います。市子連では実体験に基づく活動を通して、思い出に残る魅力ある行事をしていきます。
~松本さんのはなし(23)~
3月に入り気候も徐々に春らしくなってきましたが、寒い日があったりもします。春先のこの時期、三寒四温と言って寒くなったり、暖かくなったりを繰り返して、春に向かっていくのだそうです。
そうした中、2月2日(日)(今年はこの日が地球の自転の関係で節分にあたりました)市子連にとって最も大きな行事である「新春子どもフェスティバル2025」を中央公園、市役所、四番丁スクエア体育館・運動場などを会場に「さむさに まけるな かぜのこ よいこ」のテーマのもと開催しました。なぜか今回も昨年と同じように前日の準備の時点から雨が降り出しました。(しかも夜から朝まで結構の雨量)当日の朝、四番丁スクエアの運動場にチェックに行ってみると、スポンジで吸い取れるレベルではないくらいの水たまりが広範囲に広がっていました。楽しみにしていた子どもたちには残念な思いをさせましたが、仕方なくドッチボール大会は中止としました。もう一方の外で行う中央公園での行事は水たまりを避けてテントの位置を移動するなどして、なんとか開催することができました。すもうやかるた取り大会に真剣に取り組む子どもたちや一生懸命に応援するお父さんやお母さん、笑顔あふれる一日となりました。今回は天候の影響で変更を余儀なくされましたが、その時々に皆さんが知恵を出し合って、最後の片付けまで無事終えることができました。参加者が少なくなってきている現状からいろいろな意見もあるとは思いますが、こうした行事はなくてはならない行事、また、なくしてはならない行事であると改めて思いました。役員をはじめ多くの関係された皆様本当にありがとうございました。
来年度は会場の関係からいろいろと変更しなくてはならない事案が多くあります。今まで通りの行事内容にとらわれることなく子どもたちの笑顔のために準備していこうと思っています。ご協力をよろしくお願いします。
そして、2月 24日(日)には香南アグリームにて各校区の子ども会リーダーを対象とした、子ども会リーダー研修会を行いました。収穫体験としてイチゴ狩りと調理体験として手作りウインナー作りをしました。今回はありがたいことに参加者が多く盛況でしたので、午前のグループと午後のグループに分けて行いました。
イチゴ狩り体験は最初に施設の人からイチゴの採り方などの説明を聞きました。私も初めての体験でしたが、そっとつまんでくるっと返すと意外に簡単に摘み取ることができ、子どもたちも渡された容器に収まらないほど山盛りに収穫していました。
ウインナー作りは初めての子どもたちが多くいましたが、こちらも指導してくださる方が丁寧に教えってくださって、皆失敗すること無く上手に作ることができました。
最後に焼きたてのパンとサラダと一緒にいただきました。子どもたちからは自分で作ったので、とてもおいしいとの感想が聞けました。
市子連ではこうした実体験をもとにした体験活動を多く取り入れた行事を企画、実施しています。子どもの頃に体験したことはとても重要です。これからも参加しやすく、魅力ある行事をしていきます。
~松本さんのはなし(22)~
暑さ寒さも彼岸までという慣用句があります。そのようなこともあって、今年のフットベースボール大会はすこし涼しくなるだろうとの想定のもと(実際はまだ暑く真夏並みの天候が続いていましたが)、9月22日(日)に開催しました。数日前より当日の天気がどうも雨らしいという予報。秋の天気は変わりやすいとの淡い期待もむなしく、前日になっても雨予報は変わりませんでした。
前日は晴れていたので準備は晴雨どちらでも対応できるような形で行い、そして、当日の朝となりました。「あの雲があっちに流れて、こっちが明るいので、天気は良くなる。よし!できる!」曖昧ではあるけれど、希望と確信に満ちた判断をし、開催を決定しました。役員の方には7時に集まってきてもらって、開会の準備を段取りよく進めて、いよいよ開会となった時、少し雨がパラパラと降ってきました。子どもたちが夏の暑い中練習をして今日を迎えていると思うと、やるしかないという思いが強くなり、「少し雨が降ってきましたが、やりましょう。」とあいさつをすると、子どもたちからは元気な声が返ってきました。
小雨が降ったり止んだりする中、第1試合が始まりました。子どもたちの真剣な眼差しや、元気にプレーする姿……。「やっぱり、やってよかった~。」少し薄日も差してきたりして、よし。このままこのまま……。その願いもむなしく第2試合が始まって少したったとき、西の方から黒い雲がこちらの方に来てるなと言ったとたん、雨がザーッと降ってきました。一旦、小降りになったので、子どもたちにどうするかを尋ねると「する、する、ぜったいやりたい。」との声と訴えかける目。「よし!やろう!はじめてください。」と再開したところに、今度はどうすることもできない大雨が。もうこれ以上は無理と判断、子どもたちも納得し、中止を決定しました。
その後、体育部や役員の皆さんでずぶ濡れになっての片付けとなりましたが、とにかく無事に終えることができました。この大会にご尽力くださった皆様、本当にありがとうございました。ある意味思い出に残るフットベースボール大会でした。
現在は、来年2月2日(日)に開催される「新春子どもフェスティバル2025」に向けての準備を、おまつり部の皆さんが中心となって着々と進めています。10月24日・26日両日にはそのフェスティバルで行われる「かるたとり大会」の審判講習会を開催しました。10月後半にもなっているのにも関わらず、半袖で過ごせるくらいに暑く感じる中ですが、多くの方が参加してくださっていて、「かるたとり大会」に寄せる皆さんの熱い思いを感じています。
「新春子どもフェスティバル2025」も皆様のお力をお借りしなければ成り立たない行事です。子どもたちの笑顔あふれる、楽しい一日なるように、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
~松本さんのはなし(21)~
朝の蝉の声がしなくなり、夏から秋へと移りつつあるかと思うと何となく寂しく感じられるようにはなってきましが、まだまだ厳しい暑い毎日が続いています。そうした中、市子連の行事をすこし振り返ってみることにしました。
5月11日(土)に市子連総会を加藤副市長様、小柳教育長様をはじめ多くのご来賓の方々のご列席のもと開催しました。はじめに、長年、育成会に貢献いただいた方々に感謝状の贈呈をしました。また、本年度は役員改選がありましたが、皆様の承認を得ることができ、無事出発することができました。皆様ありがとうございました。
6月16日(日)に塩江のセカンドステージにて、新たに役員になられた方を対象とした新役員講習会を開催しました。前半のグループ討議では、各校区の子ども会行事の取り組み等をそれぞれに紹介していただきました。子どもたちの参加が少なくなってきているという課題がどこの校区でもあがっていました。参加者が少なくても簡単な形でいいので、施設等を利用するなどして負担のかからないように工夫をして、とにかく行事を続けていくことが大切だとのまとめになりました。後半は校区や地域の子ども会の行事等で役に立てていただけるように、体験活動としてピザ作りをしました。何かを作って食べるという作業は、ただ、ものを作るだけではなくお腹の方も満足します。子どもたちにも楽しくいい企画になると思いました。今回のような体験活動を取り入れた育成者参加行事は秋にも予定していますので、是非、参加してみてください。
6月22日(土)フットベースボール審判講習会を亀阜小学校で、昨年と同様の形で開催。ルール説明の後、亀阜校区の子どもたちの協力を得て実践形式で審判の練習をしました。年々フットベースボール大会にエントリーする校区が少なくなっています。今回の審判講習会も参加される方が少なかったことからも、行事の在り方や方法を考え直さなければならないと思っています。
7月 6日(土)子ども会リーダー研修会を早明浦ダムとその近くにある「いしはらの里」で行いました。今回、子どもたちも多く参加していました。最初の早明浦ダム見学ではこの度の工事は、温暖化の影響で、近年、異常気象でゲリラ豪雨等が頻繁に起こるようになったことから、放流をスムーズにするための工事との詳しい説明を聞いた後、実際に皆でヘルメットかぶって工事中の現場に連れて行ってもらいました。ダムの中間当たりに穴を開けるという大変な工事の様子やその工法を聞きました。子どもたちには少し難しかったかもしれませんが、今でしか見られない貴重な工事を見ることができました。その後「いしはらの里」へ行ってバームクーヘン作りを体験しました。暑い中、火のそばでより熱い思いをしながらの体験でしたが、それぞれの班ごとに個性的なバームクーヘンができました。施設の方もとても親切で、昼食には羽釜で炊いたご飯をいただき、また、次の日が7月7日で七夕ということもあって、自分たちの願いごとを短冊に書いて笹に飾ってもらったりもしました。子どもたちには夏のいい思い出になったと思います。「いしはらの里」は廃校になった学校を活用していて、、野外活動や宿泊もできる施設です。近くにはきれいな川が流れていて、アメゴのつかみ取り体験や山登りや川遊び等もできるとのこと、今後のリーダー研修会の候補として参考になりました。
それから一週間後の7月13日(土)、市子連会長理事研修会を生涯学習センター(まなびCAN)で開催しました。講師に大佛早苗氏をお迎えして「育児が楽になる食事の基本」~超シンプルでみんな元気いっぱい~と題しての講演をしていただきました。日本人の体(体質)にはパンよりお米がいいという内容で、パンにはバターが多く使われているので、大げさかもしれませんがかき揚げを食べているようなものです!や、ジュースやコーラ、缶コーヒー等には砂糖がいっぱい使われていて、具体的に砂糖のスティックが約何本分使われています!など目からウロコの内容で、これからの食生活や子どもたちの食事についても気をつけていこう思いました。
その後会場を移動して、市子連懇親会を5年ぶりに開催しました。大見市議会議長様、小柳教育長様をはじめ多くのご来賓の皆様にご列席いただき、現役の会長、理事さんやまたOBの方も交えて、これからの子ども会や現状などを話したり聞いたりしました。今回の懇親会が校区や地域の今後の活動に於いて少しでも励みになってくれればと思っています。現実は厳しいものがありますが、子どもたちのために子ども会はなくてはならない存在として有り続けていこうと決意を新たにする有意義な懇親会となりました。ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。
~松本さんのはなし(20)~
あちらこちらで花が咲き春真っ盛りの今、今年に入って早くも三ヶ月が過ぎてしまいましたが、その間の市子連行事を少し振り返ってみましょう。
2月4日(日)に「新春子どもフェスティバル2024」をコロナが5類に移行したことから、4年ぶりに元の形に戻して開催しました。この行事は子どもたちも楽しみにしていて、また多くの方の協力を得て準備も時間を掛けて行うもので、市子連最大の行事になります。前日の夜から当日の朝までの雨でグランドに大きな水たまりができましたが、多くの人の影での支えや迅速な対応で、子どもたちの笑顔にあふれたフェスティバルができました。準備から片付けまで実行委員の皆様本当にありがとうございました。(私事ですが、終了後二日間ほど疲れが取れませんでした。とても疲れた記憶があります。皆様本当にお疲れ様でした。)
2月18日(日)には各校区の子ども会リーダーを対象とした研修会を昨年度と同様、男木島で開催しました。港からほど近くの男木コミュニティセンターから男木島灯台、水仙郷エリアを目指してウォーキングをしました。(男木島に初めて来たという子どもたちも多くいました)群生している水仙の花と瀬戸内の海や島々、石造りの灯台と青い空、男木島に行かないと味わうことができない自然や風景を、子どもたちが感じ取ってもらえたらいいなと思いながら、今回は島を一周するコースで歩きました。次年度もいい企画なので続けていければと思います。
3月9日(土)県立文書館で市子連行事の締めくくりとなる「活動推進大会」を開催しました。はじめに、子ども会のためにご尽力してくださった方に感謝状の贈呈を行いました。今後も地域や子どもたちのためにご協力をお願いします。木太北部校区の活動報告では、子ども会活動を地域の協力を得ながら工夫して地域全体で活動している様子が紹介されました。そして、子どもたちが思い出に残る魅力あるイベントを続けていく事で、サポートしてくれる保護者が増えたことなども参考になりました。それから、今回は初めての企画として「パネルディスカッション」をしました。役員のなり手不足もさる事ながら、そもそも子どもの数が減って活動ができなくなっている現状が報告されました。課題山積の子ども会です。どうすればいいかを皆さんともう少し話し会えれば良かったと思えるディスカッションでした。これからもこうした機会をもっと増やしていこうと思います。
今現在は5月の総会に向けて準備をしています。次年度も子どもたちのためにワクワクする内容の企画をしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
~松本さんのはなし(19)~
今秋は各地でお祭りが4年ぶりに通常通り復活開催され、子どもたちもお祭りに参加するなど、特色のある伝統行事に触れる機会が増えたことだと思います。私の地元でも子どもたちが太鼓台(ちょうさ)を引きながら歌う元気な伊勢音頭の歌声が響いた秋でした。
市子連でも来年2月4日に開催される「新春子どもフェスティバル2024」を4年ぶりに通常通りに戻して開催しようと、おまつり部が主体となって準備を進めています。その中で、11月 10日と12日の両日にはフェスティバルの競技種目の「かるた取り大会」の審判講習会を行いました。両日とも多くの方が参加されて、皆さん熱心に受講されていました。こうした様子を見ると、コロナを少し引きずっていた昨年とは皆さんの気持ちが大きく変化していると感じました。
また、11月 23日(木・祝)には「育成会指導者講習会」(各校区の育成者対象)を研修部の発案で琴平にて開催しました。香川県に住んでいても金比羅さんに行くのも久しぶりと言う方が多くいました。(私もなんと小学校の遠足以来です)午前中はこの時期にしては最高気温が21℃と暑いくらいの陽気の中、汗をかきかき金比羅さんの石段を上り参詣し、その後、希望者で金丸座の見学をしました。案内の方が詳しく説明してくださり、また隅々までよく見ることができとても良い経験になりました。昼食後、和三盆作り体験をしました。最初に和三盆の説明(何故和三盆と呼ばれているか、讃岐三白とは等)を受けて、木型に和三盆を詰めてお菓子を作ります。完成後、抹茶と一緒にいただきました。残りは小さな綺麗な小箱に入れて、お土産として持ち帰りました。子どもたちにもできる内容で、和三盆の歴史も学べてとてもいいと思いました。市子連ではこのような講習会を今後も開催していきます。校区や地区の子ども会行事の参考にしていただければと思います。
2023年も残りわずかとなりました。ニュース等の映像で、戦闘によって子どもたちが悲惨な状況になっているのを目にします。もどかしく、心が締め付けられそうになります。未来を託す子どもたちがにこやかに暮らせる日々が早く来ることを願うばかりです。世界がこのような中、皆様のご協力により子ども会は今年も無事に行事を終えることができました。本当にありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。よいお年をお迎えください。
~松本さんのはなし(18)~
夏休みが終わり、9月に入ってもまだ厳しい暑さが続いている中、小柳教育長様をはじめご来賓の皆様をお迎えして、9月 3日(日)に第52回高松市子ども会フットベースボール大会を高松市西部運動センターで開催しました。
新型コロナウィルス感染症が5類へと移行してからは、地域のおまつりやイベント等もコロナ前に戻していこうとする動きが活発になってきており、市子連の行事についても同様に戻していっています。しかし、一期間とはいえ一旦コロナで途切れてしまったこのような子ども会の行事は、子ども会役員の方がコロナの間に交代しているケースもあり、行事継続において結構根深く影響を及ぼしています。
今回のフットベースボール大会でも、以前からエントリーする校区が年々少なくなってきたところへ今回コロナの影響を受けて、益々少なくなっているのが現状です。こうした状況の中でも、子どもたちを集めて夏休み中練習をし、大会に参加された校区の役員の皆様には大変に苦労したことだろうと、本当に頭の下がる思いでした。
暑い中での開催とあって、運営面においても暑さ対策等に知恵を出し合って臨みましたが、まだまだ不十分な点もあり、開催時期、進め方等、今回も反省点は多々あります。それでも表彰式でメダルを掛けてもらった時の子どもたちのニコニコした表情や記念にフットベースボール大会の幕の前で写真を撮ってもらっている時の喜ばしく誇らしい笑顔を見ると、過酷な中ではありましたが、やって良かったなと思っています。この夏、暑さの思い出とともにフットベースボール大会の思いでも子どもたちの記憶に刻まれ、また、スポーツを通して子どもたちの心の成長に確実に貢献していると信じております。
どのような時代になろうと、アプローチの仕方は変化しても子ども会の果たす役割は変化するものではないと思っています。子ども会行事を進めて行くにはその年々で、これからも色々と困難なことがあるかもしれません。この大会を通じ子どもたちの笑顔に触れることができたことで、昨年と同様たとえ少ない人数であろうと、小規模になろうと、とにかく続けていくことが大切だと実感しています。
最後になりますが、ご協力いただきました校区役員、市子連体育部、審判員、その他この大会に携わってくださった多くの皆様ありがとうございました。
~松本さんのはなし(17)~
子ども会行事が各校区で徐々に高まりを見せる中、市子連では9月に行われるフットベースボール大会の審判講習会を6月 24日(土)に亀阜小学校にて開催しました。毎年この時期に審判が初めての方や興味を持たれている方を対象として、方試合方法や競技規定についての講習を受けてもらって、当日の審判をしていただいています。この日は亀阜校区の子どもたちの協力で実践形式での審判の練習も経験でき、有意義な講習会となりました。
7月 1日(土) 、子ども会活動をする中で、疑問に思ったり、不安に感じたりすることを一緒に考えていこうということで、「校区子ども会育成連絡協議会会長・役員交流会」を瓦町フラッグ会議室等で開催しました。情報交換会では、8校区17名の方が参加してくださり、それぞれの校区の現状とか、また、活動費の事など皆さん赤裸々に語っていただきました。その後の交流会でも、“子ども会の役員は色々と大変だけどやりがいがある”ということで認識が深まり、これからの子ども会活動に励みになる交流ができたと思います。今回参加できなかった校区もありますので、また機会があれば、こういう場を設けていきたいと思っています。
3週続いて7月 8日(土)には、「高松市子ども会リーダー研修会」を開催、高知のYASU海の駅クラブでシーカヤック体験やNHK朝ドラの「らんまん」で脚光を浴びている牧野植物園の見学学習をしました。参加対象は各校区の子ども会リーダーです。最初に子どもたちに聞きました。「今日、各校区の子ども会のリーダーとして自覚を持って参加した人~」……ひとりも手が上がりません。そうなるとは思っていました。切り替えて、「この研修会はリーダーになるための研修会です。皆さん最後まで楽しく頑張りましょう。」
さてさて、そうした中、シーカヤックの体験活動が始まりました。真剣にインストラクターの先生の言うことをよく聞いて、ライフジャケットを装着。力を合わせてシーカヤックを浜辺に運搬。そして、パドル操作の練習やカヤックの乗り方などのレクチャーを受けて、皆、怖がることなく海へとカヤックを漕ぎ出していきました。それから暫くして元の浜辺に帰ってきました。早く帰ってくることができた子どもたちは、後から帰ってきた子どもたちがカヤックから下りるのを手伝ったり、一緒にカヤックを運んだりと、大人があまり手助けしなくても、子ども同士で協力してテキパキとカヤックを洗ったりの片付けも、とても早くスムーズにできていました。インストラクターの先生も「四国それぞれの県から子どもたちがここへ来ますが、香川の子どもたちが、一番よく話を聞いて、元気もよく良いですね。」と褒めていました。
その後の牧野植物園でも班ごとに時間通りに行動ができ、バスも市役所に時間通りに無事帰ることができました。バスから降りてきた子どもたちは皆、少し日焼けをした精悍なリーダーの顔つきになっていました。実体験に勝る勉強はないなと改めて思わされるリーダー研修会でした。
他校区の子どもたちとの交流や、少し自由度を持った内容の体験活動は、子ども会だからできる独特なアクティビティだと思っています。市子連では、日程、場所は未定ですが、今年度もう一度、「子ども会リーダー研修会」を予定しています。多くの子どもたちの参加をお待ちしております。
~松本さんのはなし(16)~
新年度に入り、5月 8日以降新型コロナウィルス感染症も5類へと移行されたことから、学校行事や地域での行事も徐々に活発に(泊を伴う行事も)行われるようになりました。子どもたちの様子も以前よりとても活気が出てきたように感じます。
そうしたなか、5月 13日(土)大西高松市長様はじめ多くのご来賓をお迎えして、総会を開催しました。はじめに、校区子ども会の会長や市子連理事をされ、市子連の活動を推進し、貢献された方に育成功労者感謝状の贈呈を行いました。長年、多方面で市子連の活動を支えてくださり、本当にありがとうございました。今後も子ども会や子どもたちのためにお力添えをいただければと思います。続いての議事についても、皆様のご協力で承認を得ることができました。ありがとうございました。今年度は、コロナで実施が難しかった、体験活動を中心とした活動が積極的にできると思っています。
そして、5月 21日(日)には、新しく子ども会の役員になられた方を対象として、新役員講習会を塩江セカンドステージで開催しました。
前半の情報交換・質疑応答では、少子化で子どもの数が減少していく中、役員も同様に減少し、子ども会を維持していくのが困難になってきているといった現状について、他校区の工夫した活動を通して話し合うことができました。市子連としてもこうした課題に対して皆さんと一緒に考える機会として、「校区会長・役員交流会」を企画しています。(詳細はホームページに掲載)率直な意見や現状を言ってもらって、子ども会を持続可能なより良い方向へと進めていければと思っております。多くの方のご参加をお待ちしております。
また、後半は体験活動として、「竹で炊き込みご飯作り」をしました。初めての試みだったので、期待と不安で一杯だったのですが、私的には「ん……」といった感じで不安が的中。(おいしくできた方もいたとは思います)、どちらにしても、とにかく炊くのに時間がかかりました。参加された方には終了時間が遅くなってしまい申し訳なく思っています。こういうことも体験しないと、わからなかったことです。実際にやってみることが大事なことだと実感した「竹で炊き込みご飯作り」でした。
~松本さんのはなし№15~
3月 4日(土)市子連行事の締めくくりとなる「高松市子ども会活動推進大会」を小柳教育長様はじめ、ご来賓の方のご出席のもと開催しました。
はじめに、育成功労者感謝状と優良子ども会に表彰状の贈呈を行いました。表彰を受けた皆様、長年子ども会活動にご尽力くださりありがとうございました。引き続き子どもたちのために、地域の良きアドバイザーとしてご指導くださればと思います。よろしくお願いいたします。
続いて、弦打校区キッズクラブと木太北部校区子ども会の事例発表がありました。両校区とも地域の子ども会以外の団体とコラボしての活動が報告されていました。中にはスポーツ少年団(スポ少)と一緒になっての行事というのもありました。子ども会とスポ少は行事の日程が重ならないようにお互いに気を遣ったりして、どちらかと言えば対立(少し大げさかも)するような関係で、コラボすることはあまり無かったように思います。そのようなことからも、とても画期的な事だと感じました。この事例のように他団体とのコラボも発想を変えることで、ウィンウィンの関係になることはいっぱいあると思います。
また、内容に関しても、弦打校区の防災を取り入れたキャンプ、木太北部校区の自己肯定感を子どもの頃にいかに感じさせるかということを真剣に取り組んだ行事と、とても高度で、「もうこれは子ども会のレベルを超越している……。私が子どもの頃経験した“昭和の子ども会”とは違っていて、『子ども会』という名前も変えた方がいいのではないか?……。」と思われるような内容で、子ども会もここ数年で大きく変化してきていると実感ました。
今回の活動推進大会はこれからの子ども会の運営のヒントとなるような内容が多くあったと思います。事例発表をしてくださった弦打校区、木太北部校区の皆さんありがとうございました。校区によってそれぞれ状況は異なると思いますが、参考にしてとにかく楽しい子ども会を目指していきましょう。
~松本さんのはなし№14~
立春となって一日目、まさしく春を思わせるような暖かな陽気につつまれた2月5日(日)「新春子どもフェスティバル2023」が、三年ぶりに盛大に開催されました。競技種目(すもう・ドッチボール・かるた)に出場していた子どもたちも、それぞれ久しぶりの大会とあって、皆真剣さの中にも楽しんで競技していました。なかでも、かるたとり大会は、「高松わくわくかるた」を初めて使って行われ、運営側としても少し不安はありましたが、無事に進めることができました。「高松わくわくかるた」は昨年度子どもたちから募集して作られた、高松の名所など高松の魅力がいっぱい詰まっているかるたです。子どもたちがこのかるたで高松への愛がより強くなってくれればと思っています。
また、中央公園の自由参加のコーナーでも、天気が良かったこともあり、多くの親子連れが楽しく参加されていて、たいへん盛り上がっていました。今回はコロナ禍ということもあり、時間を短くして行いましたが、子どもたちの楽しそうな様子が見られて本当に開催できて良かったなと思っています。
フェスティバルから一週間後の2月11日(土)、子ども会リーダー研修会を男木島で行いました。子どもたちと港から男木島灯台や水仙郷までの往復のウォーキングをしました。この日も天候に恵まれ、歩いていると汗ばむほどでした。そうして歩き終わってきたところに、メタバースの体験イベントが催されていました。ゴーグルをつけると男木島をウォーキングできるというものでした。興味を持った子どもたちが早速体験をしていましたが、実際に歩いてみないとわからないこともあります。(男木島の風景だけではなく、道中の水仙の花々や水仙の香り、住む人がいなくなって廃墟になった家やイノシシが掘ったと思われる穴とかも目にすることができました。)市子連では、メタバースなど仮想空間を利用した社会が急速に進んでいく時代にあっても、未来を担う子どもたちには、現実的な体験活動を大事にしていこうと思っています。
~松本さんのはなし№13~
2022年もあと残りわずかとなりました。
一年を振り返ってみますと、市子連では2年間コロナの影響で開催できなかった様々な行事を、
徐々にではありますが皆様のご協力のもと進めることができました。
春には、対面での総会、新役員講習会、夏休み明けのフットベースボール大会、
そして子ども会リーダー研修会(高知県夜須)、11月には雨の中、育成会指導者講習会(小豆島)を開催しました。
皆様にはそれぞれの行事の準備や審判講習会、また各専門部会等、3年ぶりにとても忙しい一年であったのではないでしょうか。
只今、市子連では来年の2月5日に開催予定の「新春子どもフェスティバル2023」に向けて準備の真っ最中です。
この行事は多くの子どもたちが参加できる最大の行事となっています。何れの行事も皆様のご協力なくしてはできないことばかりです。今後とも子どもたちの笑顔あふれる魅力ある行事を行っていきたいと思っていますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
また、この度、皆様には「市子連会費に関するアンケート調査」をお願いしております。
昨今、PTAをはじめとして学校や地域の環境が大きく変化しており、それらの事象に直接的には関連していると考えてはいませんが、
市子連でも発足以来変えてこなかった会費の内容を変えていくことにしています。
子どもの数の減少や物価の高騰等だけではなく、時代の移り変わりと共に人々のニーズも変化しており、今まで通りの行事を維持していくには大変厳しい状況ではありますが、アンケートを基に皆様の希望に添うべく納得のいく形にしていこうと存じております。
最後になりましたが、今年一年子ども会活動にご理解とご協力を賜りありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、皆様「ブラボー!」なお年をお迎えください。
~松本さんのはなし№12~
今年の夏休み、子どもたちにとっても、久しぶりの行動制限の無い夏だったとは言え、コロナのオミクロン株の急拡大があり、
何とも悩ましい夏休みだったのではないでしょうか。
市子連でも、本年度は少しずつ行事を元に戻していこうということで進めていますが、一足飛びに元には戻せないのが現状です。
そのような中、9月 4日(日)に、第51回高松市子ども会フットベースボール大会を開催しました。
コロナの第7波が少しは沈静化に向かっていたとは言え、熱中症の危険性がある暑さが連日続き、
その上台風の接近で、前日の準備が雨のため途中で中止となる等、二重、三重と立ちはだかる壁が有りましたが、
コロナ禍で窮屈な思いをしている子どもたちに、何とか元気になってもらいたいという皆さんの熱意で、
当日は晴天となって、盛大に開催、そして、(終了間際ににわか雨がザーッと降りましたが…)無事に終えることができました。
子どもも大人も皆、笑顔があふれていて、生き生きとしていました。それぞれに友情を深め、思い出をつくることができたのではないかと思います。
この大会を通して、感じたことは、たとえ小規模でも、どのような形になっても行事をすることの大切さです。
行事をすることは確かに大変です。皆様のご協力がなければ成り立たないことばかりですが、
子どもたちのために、子ども会らしい行事をこれからも行っていこうと思っています。
最後になりますが、暑い中、この大会に携わってくださった、校区の役員、審判員、体育部、多くの皆様、
本当にありがとうございました。おかげさまで、とてもいい大会となりました。
~松本さんのはなし№11~
清々しい新緑の季節から一気に夏らしくなって来ました。
体がなかなか順応していけないところ、なんとコロナウイルスがだいぶん収束してきました。
少しずつ元の生活に戻そうと、様々なイベントも復活させていこうという動きになってきております。
会話の中でも以前は、「コロナ」、「自粛」、「ワクチン」などのワードが多く使われていましたが、
このところ、「3年ぶり」が今年の流行語大賞になるのではないのかと思われるくらい、あちらこちらで
「3年ぶり」が使われるようになっています。
市子連でも、5月14日に「3年ぶり」に対面形式で総会を開催しました。
また、6月19日には、「3年ぶり」に新役員講習会も開催でき、梅雨の時期でしたが天気にも恵まれ、
塩江セカンドステージで、講話とピザ作り(生のバジルやイタリアンパセリなどを各自で採りに行って、
トッピングして……)をしました。そして、9月にはフットベースボール大会、リーダー研修会と、
こちらも「3年ぶり」の開催を計画しております。
さて、「3年ぶり」「3年ぶり」と続いたところで、その約15倍「46年ぶり」に「かるた」をリニューアル!!
新聞、ラジオ、テレビのニュースなどにも、とりあげていただきました。
各校区へも新しいかるた「高松わくわくかるた」が配布されていることだと思います。
来年の2月「3年ぶり」の新春子どもフェスティバルのかるたとり大会から使いたいと思っています。(今からそれこそ、“わくわく”しています)
これから、夏休みに向け各校区や地域の子ども会でもキャンプなど、いろいろと計画されていることだと思います。
子どもたちの笑顔あふれる行事が少しずつでもできるようになって、本当に良かったなと思っています。
~松本さんのはなし№10~
4月は、子ども会にとっても新旧入れ替わりの時期であり、
皆様方も引き継ぎ等とても忙しくされていることと思います。
市子連におきましても、3月に締めくくりの行事である
活動推進大会を、皆様の御協力で無事に終えることができ、
今現在は5月14日の総会に向けての準備をしている最中です。
今回の総会は2年間続けて書面決議になっていましたので、
状況が良く開催されるとなれば、3年ぶりの総会となります。
あらゆる行事がコロナの影響を受けて暫くできていなかったので、
勘を取り戻すのにも大変になっていますが、皆さんの校区ではどうですか…。
さて、以前募集していました「高松わくわくかるた」ですが、
42の小学校から537作品もの応募がありました。
とても嬉しく思っています。
また募集の際には、各小学校や校区の皆様に大変お世話になりました。
ありがとうございました。
何度も何度も選考し「あ~わ」までの44音の作品が決まり、
ただ今「かるた」を作成中です。もう少しお待ちください。
また、6月8日(水)~14日(火)には「子ども会活動報告・高松わくわくかるた」
としての展示を市民交流プラザIKODE瓦町展示コーナーで行うこととなっています。
子どもたちの力作を見に来てもらったらと思っています。
令和3年度は子どもたちが参加する行事ができませんでしたが、
来年度は感染対策をして何とか子どもたちの笑顔あふれる行事ができればと思っています。
この一年間、子ども会また市子連に、ご支援くださり、ありがとうございました。
来年度もどうぞよろしくお願いいたします。
~松本さんのはなし№9~
2021年もあと残りわずかとなりました。
子ども会もコロナウイルスの影響で、ここ2年間振り回されました。
この秋以降、感染者の数もぐっと下がり、少しずつ活動を再開できると期待していたところに、
またしてもオミクロン株という変異したウイルスが世界中に広がりを見せています。
ワクチンの効果で重症化はしないだろうと言われてはいますが、
漸く動き始めた子ども会活動が鈍くならなければいいなと思っています。
市子連でも、今年度に入って子どもたちと交流のできる活動ができていませんでしたが、
現在、来年2月6日の「新春子どもフェスティバル」の開催(縮小しての開催)に向け、計画を進めているところです。
話は少し変わりますが、その新春子どもフェスティバルのかるたとり大会で、
長年(約40年間)愛用されている「よいこのかるた」、この「かるた」は環境問題に重点を置いていて、
当時の子どもたちの先見性に感心させられるとてもいい「かるた」だと思っています。
この度、その「よいこのかるた」を残しつつ(惜しまれる方もおりますので)、
時代の移り変わりや、高松市も合併に伴い広くなったこともあって、
高松の自然、人物、産業、場所、特産物やお祭りなどの行事とかをテーマとした、
子どもたちが「故郷高松」をよく知り、未来へ伝えていけるきっかけとなるような「かるた」も
作ろうということとなりました。(今回のかるたとり大会は「よいこのかるた」を使います)
現在、かるた募集要項のチラシを学校から配布していただいております。
この冬休みに親子で考えてみてもいいかなと思いますので、ぜひ挑戦してみてください。
最後になりましたが、今年一年コロナ禍の中、子ども会活動たいへんありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
よいお年をお迎えください。
~松本さんのはなし№8~
この夏のコロナの全国的な感染拡大はいったい何だったのか……。
秋の訪れとともに感染者が急速に減少し、香川でも感染者無しの日が何日も続くなど、
大分落ち着いた状況になってきました。このままこの状況で、ずっと続いていってくれればいいなと思います。
子ども会行事も完全に元に戻すとまではいきませんが、少しずつ進めていけるようになってきました。
10月 8日(月)には、久しぶりに執行部会をしました。
そして10月21日(木)には、市子連最大のイベントである「新春子どもフェスティバル」に向けての
おまつり部会がありました。
昨年は高松市のような大きな単位で、広いエリアから子どもたちが集まってくるのは、
感染リスクが高まるとの理由から早々と中止が決定されましたが、
今回は開催時点での状況にもよりますが、縮小した形でなんとか開催しようということになりました。
(詳細については、もう少しおまつり部会で詰めて11月26日(金)の理事会で発表したいと思います)
また、先日11月 2日(火)には研修部会があり、11月27日(土)に開催する
「育成会指導者講習会(香南アグリーム)」の内容確認や「子ども会リーダー研修会(冬)」の
楽しい企画案を検討したりしました。
皆さんの地域や校区でも、工夫していろいろと行事が行われていると聞いています。
計画通りに進められなかった時期から、「減少している今がチャンス」と、急に忙しくなってきて、
役員になられた方も気持ちや頭の切り替えが大変だとは思いますが、
久しぶりに子どもたちの笑顔が見られる行事がやっとできるのかと思えば、
楽しく感じられる今日この頃ではないでしょうか……。
~松本さんのはなし№7~
7月 2日(金)体育部会が行われました。
昨年はコロナの影響で中止となったフットベースボール大会でしたが、
体育部会の皆さんの熱意で、感染防止対策をしっかりと取った上で開催しようと言うことになりました。
そして、7月 9日(金)には研修部会が行われ、県内、日帰り、飲食はしない等感染リスクを
避けた様々な制約をクリアした内容を研修部の皆さんで知恵を出し合って考え、
津田でシーカヤック等の研修をすることに決めました。
以上の決定に基づき体育部では、用具の点検、審判委嘱式、出場チームの抽選会など
着々と準備が進められ、また、研修部でも研修会場(クワタラソさぬき津田)の下見をして、
施設の方との打ち合わせや、参加者の募集を募る等、こちらも準備が進められていました。
そのような中またしても新型コロナウイルスの感染が全国的に急増、香川県でも同様の状況が見られることから、
8月 3日 香川県独自の警戒レベルが上から2段目の「感染拡大防止集中対策期」に移行され、
さらに 8月 9日 には警戒レベルが最も高い段階の「緊急事態対策期」に引き上がりました。
今年こそはなんとか工夫して実施できると思っていた市子連の行事の「リーダー研修会」や
「フットベースボール大会」でしたが、子どもたちの安全面を考慮すれば、
残念ですが中止せざるを得ないと判断しました。
子ども会はいろいろな行事をすることで、価値が生まれます。
その行事ができないとなれば、子ども会にとっても緊急事態です。
本当に早く元のように、子どもたちの笑顔あふれる行事ができないかなと願うばかりです。
~松本さんの話№6~
今年度初めてとなる市子連の理事会が、6月12日県立文書館で行われました。
5月に開催する予定でしたがコロナの感染が急増したため、延期しての開催となりました。
今回新しく理事になって戸惑いながら来られた方や、
いつもお目にかかっている馴染みのある方、忙しい時間帯ではありましたが、
多くの方に出席していただきました。ありがとうございました。
昨年度はコロナに明け暮れた年でした。よ~し!今年度はいろいろとできるかもと思いきや……。(まさかの2年目……)
変異ウイルスの脅威もあり、子ども会活動を完全に元に戻すにはもう少し時間がかかりそうです。
マラソンか何かでへとへとになってやっとゴールも近くなって終わりかけたところで
「ここはゴールじゃないです まだ先の方ですよ」「え~っ!」という感じでしょうか。
皆さんの地区や校区では子ども会行事はどうしていますか?
また昨年のような『子ども会行事に関するアンケート』をとりたいなと思っています。
(情報を知ることは、こういう時は大事だと思いますので)そして、それを参考にしてもらえればと思っています。
各専門部(おまつり・文化・研修・体育)やジュニアリーダー
(子ども会をサポートする高校生や中学生のおにいさん・おねえさんたち)も動き始めました。
状況を見ながらの行事の遂行となりますが、何とか工夫して進めていくしかないと思っています。
子どもたちの笑顔のために楽しくやりましょう。
~松本さんの話№5~
市子連行事の締めくくりとなる活動推進大会が3月6日県立文書館で行われました。
前回、コロナの影響で中止となったため今回は二年ぶりの開催でした。
感染対策として時間も人数も制限しての開催となりましたが、
参加された皆さんの真剣さが伝わってくる大会でした。
ワクチン接種が進み少しは状況も良くなってくるだろうと期待していますが、
未知の感染症なのでまだまだ気を緩めてはいけないと思っています。
市子連としても、まだ暫くは状況を見ながら行事を進めていく方向です。
さて、コロナ、コロナと言っている間に進められているのが学校現場での
ICT(情報通信技術)を活用した教育です。
小学校でも一人一台のタブレットの配布が完了し、これを使っての授業が次々と
考えられています。まだ始まったばかりですが、いろいろと便利になっていくのかなと思います。
ふとこんな光景が……。
児童「先生~……がわかりません」 先生「先生に聞く前に指を使って調べなさい!指を!」
そして子ども会ではこんな光景が、「飯盒炊飯したことある人~」「は~い」
その子の手にはなんとゴーグルが……。(もしかしてバーチャル?)
もう何年もしないうちに当たり前の光景になっているかもしれません。
私的には子ども会は何処までも、面倒くさい事をより面倒くさくして活動し、
たとえ、ガラパゴスだ!シーラカンスだ!はたまた化石だと言われようがアナログを貫きたいと思っています。
子どもたちには、実体験に基づく体験活動をどんどんしてもらって、機械(タブレットやゴーグル)に
頼らなくても生きていける力を子ども会活動で身につけてもらいたいと思っています。
今回で今年度の「松本さんのはなし」は終わります。
一年間、子ども会また市子連に、ご支援くださり、ありがとうございました。
来年度もどうぞよろしくお願いいたします。
~松本さんの話№4~
2020年もあと残りわずかとなりました。
新型コロナウイルスの影響で、市子連でも予定されていた行事が中止になるなど、
殆どの行事ができませんでした。
また、来年2月に予定されていた市子連最大のイベントである
「新春子どもフェスティバル2021」も感染拡大防止の観点から早々と
中止を決定しているという状況です。
子ども会は子ども同士の交流や実体験に基づく体験活動を通して、
子どもたちを育成することも目的の一つにしていますが、
「3密を避ける、ディスタンスをとる」など子ども会活動とは正反対の行動を強いられ、
今回のことは子ども会にとっても大きな試練となりました。
皆さんの校区や単位子ども会でもいろいろと悩んだり、
決断をしなければならなかったりとお互いに大変に苦労した一年であったことだと思います。
子どもたちの地域社会との交わりが希薄になってきていると叫ばれている昨今において、
子ども会はなくてはならない貴重な存在であります。
また、その活動は子ども会という枠を超えて地域にとってもますます重要になってくると思います。
にもかかわらず、コロナウイルスの感染拡大が衰えるどころか増大し、
世界では新しく変異したウイルスが拡大しているとのこと……。
市子連でもよりいっそう気を引き締めると同時に、何とか工夫してできることを
考えていくしかないのかなと思っています。
話が少し長くなりましたが、来年が皆様にとって、
また子ども会にとっても明るい年になることを願っております。
今年一年ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
よいお年をお迎えください。
~松本さんの話№3~
10月 7日(水)サンメッセ香川でおまつり部会がありました。
今回の部会はとても重要な部会でした。
それと言うのは令和3年2月に開催予定の「新春子どもフェスティバル2021」を
開催するか否かを最終決定するという内容だったからです。
(開催するにも中止にするにも準備が必要なので)
おまつり部会の皆さんと市子連執行部、それに高松市教育委員会生涯学習課からも
出席しての会です。市子連の理事のおまつり部となり、初めてで何もわからないで
出席されていた人もいたのですが、そこにはただならぬ雰囲気、
そしてどこかピリリとした空気がながれておりました。
(私だけがそう感じていたのかもしれませんが) 緊張感が漂う中、
最初におまつり部の皆さんから意見を聞かせてもらいました。
各校区でのフェスティバルに向けての予選会などの取り組み、
コロナ禍でのお手伝いや子どもたちを引率する実情等とても貴重な意見が次々と…。
代替行事として何とか違う形での開催など、ねばり案も検討されましたが、
最終的には高松市のような広範囲から多くの子どもたちが集まることは、
感染リスクも増大することになり、安全面を考えると無理をして
開催しないほうがいいということに収まりました。
おまつり部の皆さんや山下おまつり部長さんにはとても重要な決定に付き合わせてしまったことに
責任を感じておりますが、難しい事柄を丁寧にまとめてくださり本当に感謝しております。
中止になったことは残念ではありますが、平成4年は盛大に開催したいと思います。
~松本さんの話№2~
8月 5日(水)に専門部会がサンメッセ香川で行われました。
新型コロナウイルスの感染が再拡大している中、皆さんマスクをして、
ソーシャルディスタンスを取っての今年度最初の部会に挑んでくださりました。
ありがとうございました。
今回初めて市子連の部会に参加された方(「何があるのかとドキドキしながら来ました」という方も)や、
久しぶりの方なども見えたりして、短時間での会でしたが各部の部長さんも決まり、
少し前に進むことができたのかなあと思っています。
子どもたちは短い夏休みが終わり、2学期が早くも始まって、暑い暑いと言いながら学校へ行っています。
9月からは7時間目の授業も再開するとのことで、子どもたちもたいへんです。
そんなたいへんな子どもたちに、子ども会として何かできないかと思ってはいますが、
気持ちだけが空回りして、結局安全面を考えると大きな行事は難しいのか…と悶々とするばかりです。
皆さんもそのようななか「他の校区ではどうしているのだろう」と思っている方もいると思います。
(実は私がいちばんそう思っているのですが…)そこで、急なことではありましたが
『子ども会行事に関するアンケート調査』を実施しました。
調査結果がまとまりましたので、紹介いたします。参考にしてもらえたらと思っています。
~松本さんの話№1~
5月28日(木)に第1回執行部会、そして先日6月26日(金)に第2回の執行部会がありました。
いずれも、新型コロナウイルス感染予防対策として、窓を開けたり、ソーシャルディスタンスをとったりの会でした。
そこで決められる事は、行事の中止……。
緊急事態宣言が解除になったとは言え、現在の世界や東京の状況を見ると、致し方ない事なのかもしれませんが、
何とかならないものかと思うばかりです。
そのような中ではありますが、28日(日)にジュニアリーダーの総会がありました。
(ジュニアリーダーは子ども会をサポートする高校生や中学生のお兄さん・お姉さんたちです)
コロナ対策をしての、とても活発な総会でした。
中止、中止で沈みがちな心がとてもさわやかになりました。爽快な総会でした。